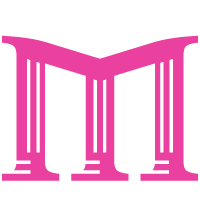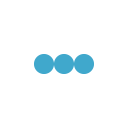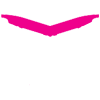- Lab-4-RetroImage.JP Museum
- 19F 理化学展示室_化学実験の部屋
- 化学実験室の「色」@大正後期の中等教育用化学参考書
化学実験室の「色」@大正後期の中等教育用化学参考書
大正期に中学校や師範学校での中等教育化学実験でよく使われていた、いろいろな試料の色味を示す彩色イラスト。本来は画像2枚で1ページなのだが、より近寄った形でご覧にいれるため敢えてそれぞれ上下に分けた。
1枚目の「粉末の色」上段の「黃燐」は粉じゃなくて蝋のようなかたまりだが、これは左隣の「赤燐」との対比のために敢えておいたのだろう。赤燐はマッチ箱の擦り付け面に硫化アンチモンなどと混ぜた「側薬」として塗ってあるくらい安定した毒性のない物質だが、黄燐はそれ自体猛毒で皮膚につくとひどい火傷を起こす上、このかたまり状態で60℃くらい、微粉末だと30℃ちょっとで自然発火して三酸化燐や五酸化二燐(十酸化四燐)といった毒ガスが発生する極めてあぶないヤツなので、とても粉末など学校では扱えない。びんの中で水に浸かっているのは、温度が勝手にあがらないようにするため。なおこの画像だとおわかりいただけないかとおもうが、黄燐の一部にニス引きしてあるのか、斜に光を当てて眺めてみるとにぶく光る部分があって、より立体的に見えるように工夫されているのが面白い。その隣の「酸化水銀」は酸化第二水銀。「酸化第二鐵」=酸化鉄(III) 、つまり鉄錆。紅殻〈べんがら〉色の顔料だが、製鉄材料としても使われていたようだ。次の「酸化鉛」は一酸化鉛(酸化鉛(II))のことで、顔料「密陀僧〈みつだそう〉」としても古くからしられていたので、明治期の化学教科書にはそう書かれていることが多い。
下段の「鉛丹」も古くからある顔料で四酸化三鉛。この粉をうっかり吸い込むと鉛中毒になる。「過酸化鉛」は二酸化鉛のことで、鉛の板にくっつけて鉛蓄電池の電極として使う。「酸化クロム」は三酸化二クロム(酸化クロム(III))で、クロム緑としての顔料や研磨材に用いる。「沃化水銀」は赤いので、沃化第二水銀(沃化水銀(II))だろう。次の「硫化水銀」は硫化第二水銀(硫化水銀(II))で、顔料の朱。本文「硫化第二水銀」項脚註の解説に、鉛丹を混ぜた朱がよくあるが硝酸で黒褐色に変わるからすぐわかる、とあることから、当時そうしたまがい物の顔料が横行していたことがしれる。
2枚目上段「クロム酸鉛」はクロム酸鉛(II)、黄鉛として顔料に用いるが発癌性物質としてしられる六価クロム化合物のひとつでもある。「ベレンス」は当時「伯林〈ベルリン〉青」と呼ばれた顔料(要するにプルシアンブルー)で、フェロシアン化第二鉄のこととしてこの本には書かれている。「綠靑」は塩基性炭酸銅(II)で、要するに銅の錆。銅器には抗菌作用があることが古くからしられていたが、この本の「銅イオン」の解説に「烈しき毒性を有し、强力なる殺菌作用を呈す」と書かれている。実際には金属の「極微動作用」(銅特有のものではなく、たとえば銀イオンにもある)による効果なのだそうだが、大正期にはまだしられていなかったのか(少なくとも昭和十年代には採り上げている論文がある
https://ci.nii.ac.jp/naid/110007119598/
)、これが恐らく「緑青は猛毒」という妄説がひろまる原因になったのだろう(くわえて、銅原料の精錬不足で砒素の混じった製品が出まわり、それで実際健康被害が出たらしいから、そのことも誤解が定着する要因になったとおもわれる)。「群靑」つまりウルトラマリンは本来青金石からつくる顔料だが、この本の「珪酸アルミニウム」項脚註には「陶土(=ケイ酸アルミニウム)に硫酸ナトリウム、炭、硫黃を混じ先づ空氣を絕ちて熱し、更に硫黃を加へ空氣を通じて熱して製す」とある。「沃度ホルム」は当時も今も殺菌消毒用の傷薬として使う。
下段「塩化金」は塩化金(III)のこととして本文には出てくるのだが、図版では金色というよりもっと赤っぽいので、これは金を王水で溶かして蒸発させると塩化水素と化合して生じる塩化金酸(これも「塩化金」と俗称されるらしい……なお本文では「之れを金鹽化水素酸と稱す」と解説してある)では、とおもわれる。「アリザリン」は本来はアカネの根から採る染料だが、ドイツでコールタールから化学合成する方法が編み出された。我が国で工業化に成功したのは大正4年(1915年)だそうだ。
https://jp.mitsuichemicals.com/jp/corporate/group/1912_1932.htm
「ピクリン酸」(=2,4,6-トリニトロフェノール—当時は「三ニトロ−フェノル」と呼ばれていたようだ)は、これも化学染料の一種であると同時に、熱や衝撃を加えると爆発する性質を利用した炸薬としても使われた。「靑藍」は「藍靛〈らんてん〉」ともいい(この本では誤って「又藍錠とも稱す」と書いてある)、要はインディゴのことで元はアイ(藍)の葉から造る染料だが、これもナフタレンから合成した化学染料に取って代わられたのは、☝の記事にもあるとおり。最後の「リトマス」はリトマスゴケ科の地衣類から採った色素で、これを濾紙に染ませたものが化学実験でおなじみのリトマス試験紙だ。リトマスゴケのなかまは☟これこれこんなヤツ。http://www.ha.shotoku.ac.jp/~kawa/KYO/SEIBUTSU/syokubutsu/CHII/kashigoke/index.html
……と、こんな調子でひとつひとつ書いていると明日になってしまいそうなので、あとは端折って。
3枚目はアルカリ/アルカリ土類金属イオン(この本では「揮發性鹽類」と書いてある)をガスバーナーの酸化炎で加熱したときの「焔色反應(=炎色反応)」と、それから針金の先に輪っかを拵えてホウ砂をくっつけ加熱してガラス球のようにした上で金属イオンをつけて酸化炎で再加熱したときの「硼砂球の反應」(還元炎で加熱すると金属によってはまた別の色になることが本文には書いてある)。どちらも今ではステンレス鋼の針金を使うこともあるようだが、当時はすべて白金線だった。4枚目はそのようにして加熱したときに発する光をプリズムで分光したスペクトル。こうやればたとえ僅かに含まれる元素であってもどれなのか特定されるから、とても近寄れない太陽やはるか遠くのほかの恒星がどんな物質からできているのかすら推定できる。なお左端の「瓦斯〈がす〉焔(有色)」はバーナーの空気取り入れ口が十分開いていなくて不完全燃焼している状態、その右の「瓦斯焔(無色)」は適正に酸素が供給されている状態を示す。
5枚目は上段左の3つが☝のリトマスの粉を試薬として、中性・酸性・アルカリ性の水溶液に加えたときの反応の様子、次の「フェノルフタレン」も同じく試薬で、試料が酸性ならば色がつかないがアルカリ性だと図のように赤っぽくなることを示している。臭素水は有機化合物の酸化による反応などをみる試薬で、また当時はジフテリアの治療にも使っていたらしい。「沃素〔酒精溶液〕」はヨウ素をエタノールで溶かしたもの、つまりヨードチンキだ。6枚目はいろいろな金属塩の水溶液。このうち「金塩」「白金塩」はガラス乾板を用いて写した陰画を感光紙に焼き付けたあと、これを鍍金〈めっき〉仕上げするときに使う(なお余計な話だが、ご存知の方はご存知とおもうけれども、写真乾板は臭化銀(silver bromide)をにかわでガラス板にくっつけたものだから、それを使った写真を「ブロマイド」と呼ぶのであって、決して「プロマイド」ではない。これは多分大正期の映画俳優写真の販売店が、間違っているのをしってかしらずか「プロマイド」と映画雑誌に広告しているのを目にした映画マニア連が何の疑問ももたず、投稿欄などでさかんに「プロ交換希望」などと使ったためにひろまってしまったものとおもわれる)。
そして7、8枚目は不揮発性の物質を精製して得た結晶それぞれの特有な色と形とを示した図。
こうした黒い背景に色をのせた図版は、コントラスト差があるだけに見る者に強い印象を与える。化学実験は色や光の変化などで人目を惹く、まるでマジック・ショウようなある種の「見世物効果」があるとおもうが、こうした色刷り図版を参考書に採り入れているのも、やはり似たような視覚効果で興味を惹きつけよう、という意図が含まれている気がする。これがあるのとないのとでは、魅力が段違いなのは否めないだろう。