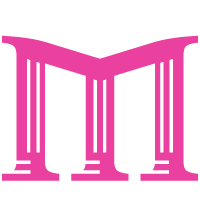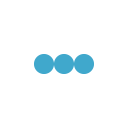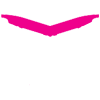- Lab-4-RetroImage.JP Museum
- 19F 理化学展示室_化学実験の部屋
- ガラス製レトルトの肖像@明治初期の薬学系無機化学入門書
ガラス製レトルトの肖像@明治初期の薬学系無機化学入門書
今日「レトルト」というと、銀色のプラ袋に密封されたカレーとかが条件反射的に思い浮かんじゃう人の方が多いのでは、とおもうのだが、本当はそれは「レトルト食品」の略であって、そうしたプラスティック容器に密封された食品を加圧加熱殺菌するための釜の方が「レトルト」そのものなのだ。
複層のプラ袋に入った常温保存可能な食品製品は、我が国では昭和43年(1968年)に発売された大塚食品の看板商品「ボンカレー」が最初とされるが、同製品特設サイトの記事によれば、これはアメリカの包装資材専門誌に載っていた軍携行食ソーセージ用パッケージの記事にヒントを得て、釜や袋の設計から独自開発された世界初の市販レトルトパウチ入り食品だったという。
https://boncurry.jp/column/brand/667/
なお、現在のレトルト食品がどのようにして作られているかについては、北海道大学水産科学研究院で公開しておられる動画がすっごく懇切丁寧な解説でわかりやすいので、ご興味がおありの方は是非ドウゾ。
https://repun-app.fish.hokudai.ac.jp/course/view.php?id=976
最後に1本だけ載っている「裏側」に出てくる缶入りーヒーの「デザイン缶」のお話など、「へぇ〜、そうだったのか〜」とおもわず感心してしまう。
ところで「レトルトパウチ」という名は英語の 'retort pouch' からきているのだろうが、フツーに考えれば「リトートパウチ」と音写されそうなものだ。それが「レトルト」となっているのは、実は幕制時代の蘭学ですでにこの語が、同じ綴りのオランダ語として入ってきていたのを引き摺っているかららしい。
https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/essay/7719/
ただしここ☝にも書かれているとおり、この「レトルト」は加圧殺菌釜ではなく、蒸留器を指していることばだった。
https://books.google.co.jp/books?id=gbBZAAAAcAAJ&pg=PP10&lpg=PP10
宇田川榕庵の『舎密開宗』をみてみると、たしかに「列篤爾多〈レトルト〉」というのがぞろぞろ出てくる。なお、ここに出てくる「蒸餾」というのは、「蒸留」の古い書き方。
「長い曲がった首のついた『蒸留器』」といえば、ウィスキーなどの製造工場にならぶ巨大な銅製のポットスティルを思い浮かべられる向きもあるかもしれない。
https://tanoshiiosake.jp/6163
お酒の単式蒸留は、原理としては全く同じだから、それは当を得た連想、ということになる。
https://www.suntory.co.jp/whisky/museum/know/jouryu/houhou1.html
ただ、「レトルト」は元々ガラスでできた、もっと小さな容器だった。
……と、まぁここまではググれば誰でもわかることだけれども、じゃあそのガラスの「レトルト」をどうやって使っていたのか、というのは何に載っているのかわからないと、なかなか見つけられないのではないかしらん。
西洋の古いものは、錬金術や化学史などの図版などにはときどき出てくるから、まだ目にする機会もあろう。
https://etherealmatters.org/media/7
だが、もっと時代が下って日本に持ち込まれた後のものとなると、却ってむずかしいかもしれない。
ということで前振りが長くなったが、今回は明治10年代に描かれた化学実験装置として登場する、細密な木口木版画による「レトルト」たちの姿をいくつかご紹介しよう。
1枚目は「尋常燐酸」(H3PO4)をつくる装置。硝酸(HNO3)を入れた「有喙レトルト」に赤燐(P)を加えて、沸騰させないように注意しながら加熱し、水で冷している右手の「受器」に蒸発したものを液体に戻しつつあつめているところ。
炉の熱源は炭火で、本文には特に解説されてはいないがレトルトのおしりに均等に熱が加わるよう、熱伝導率の高い耐火材のお皿が組み込まれているマッフル炉(間接炎式炉)とおもわれる。空中からいきなり生えているような蛇口が、なんともシュルレアリスティクな感じ。
2枚目は少量の臭素(Br2)をつくる装置。「臭化那篤𠌃謨」(臭化ナトリウム NaBr)と褐石(軟マンガン鉱のこと、つまり二酸化マンガン MnO2
https://www.flickr.com/photos/lab_for_retro_illust_japan/34197978436/in/album-72157681160012770/
)とを入れたレトルトに硫酸(H2SO4)を注ぎ込んで「重湯煎」で熱し、水冷している「受器」にあつめている。少し後ろに出てくる、「沃度化加𠌃謨」(ヨウ化カリウム KI)と「過酸化滿俺」(過酸化マンガン MnO2)との「混和物」へ硫酸を加えて同じく湯煎することで少量の「沃度」(ヨウ素 I)をつくる装置としても、全く同じ図版が添えてある。
☟の終いのところに「参考」として載せてある「臭素・ヨウ素の作り方」で図解されている、下方置換捕集の古いやり方とおもって間違いないだろう。
https://www.hyogo-c.ed.jp/~rikagaku/jjmanual/jikken/kaga/kaga40.htm
3枚目は「純粹ノ臭素化水素」(臭化水素 HBr)をつくる装置。有栓レトルトの蓋をはずして先に「臭化加𠌃謨液」(臭化カリウム KBr 水溶液のことだとおもう)で溶いた臭素を入れた球のついたガラス管をぴったりと挿し込み、レトルトの中には赤燐と水を入れてブンゼンバーナーで熱し、それからガラス管を廻して球の中身をレトルト内に落とすと「臭化燐」(三臭化リン PBr3)ができ、それが水で分解して臭化水素ガスが発生する。それを右手の「水銀槽」で水銀上置換捕集する、というやり方のようだ。
ちなみにこういう瓢箪形の水銀槽は、古い化学書ではときどき目にする。本書のもっと前の方の説明では、大理石・鋳鉄・陶器・木などで作るが、そのうち陶製のものは、かならずこのような形をしている、とある。
それから、真ん中のレトルト保持台の右手、ガラス管に熔接されている「安全管」、つまり安全漏斗管は、ガスの出が落ちてきたときに水銀が逆流してきても、うっかりレトルトに流れ込んでしまわないように取りつけてあるのだそうだ。
4枚目の図版のうち右側は「硫黄華」(硫黄泉の噴出口のところにくっついているような、硫黄蒸気の固化した黄色い粉末)を少量つくる装置。「腹部ニ副口ヲ有スル廣大ノ玻璃球」、つまり胴にもうひとつ口のついている大きな長頚丸底フラスコにごく小さなレトルトを挿し込み、レトルトの半分くらいまで硫黄(S)を入れてアルコールランプかブンゼンバーナーで焙って沸騰させてやると、レトルトのくちばしから噴き出た硫黄蒸気がガラス壁の内側に降れて急冷され、コナコナになって薄くくっつく、というもの。これは当時の硫黄製造プラントの仕組みを模したものだそうだ。
そして左側のは、いわゆるゴム状硫黄をつくっているところ。
これを試験管の手焙りでやると、結構手間がかかる☟ww
https://www.youtube.com/watch?v=EepfrZACNAw
レトルトだったら、振り回さなくても自動的にできるのかしらん……それだと楽ちんだけれど☆
5枚目は「次硝酸」(次亜硝酸 H2N2O2)をどっさり作る装置。硬質ガラス製レトルトの3分の1量のよく乾いた「硝酸鉛」(硝酸鉛(II) Pb(NO3)2)の粉を入れ、くちばしの先に「U字管」(U字状に曲げた試験管)を取りつけたガラス管をぴったり挿し込み、そのU字管は「起寒混和物」(要するに寒剤)を盛ったビーカーに突っ込む。その寒剤とは、食塩または「鹽化加爾叟謨」(塩化カルシウム CaCl₂)と雪を混ぜるか、または「硫酸那篤𠌃謨」(硫酸ナトリウム Na₂SO₄)に稀硫酸(H₂SO₄)を注いでつくる、と説明されている。
そうしてレトルトの中の塩を熱灼していくと、「其將ニ紅熾セントスルニ至レハ鹽ハ分解シテ酸化鉛、酸素及ビ次硝酸トナリ……」。
ちょっとまて。「次硝酸」って、いったい何? 硝酸鉛(II)があかく熾る摂氏470度超まで熱したら、分解して酸化鉛(Ⅱ)や酸素(O2)といっしょに出てくるのは二酸化窒素(4NO2)じゃないのか!?
https://www.you-iggy.com/chemical-substances/lead-ii-nitrate/#chemical-reactions
……とおもったら、この本の別のところにちゃんと立項されていた。「次硝酸 一名重酸化窒素 化學式NO2……」
https://www.flickr.com/photos/lab_for_retro_illust_japan/51670484034/in/datetaken-public/
ということで、なんと当時はこう呼ばれていたらしい、ということが判明。
https://www.flickr.com/photos/lab_for_retro_illust_japan/51669796546/in/datetaken-public/
次のページには、「次硝酸」が硫酸製造所で多量に使われる、とある。これは今日ではおこなわれなくなった「鉛室法」という造り方を指しているようだ。
https://www.ipros.jp/technote/basic-chemical-industy2/
6枚目の、四本脚の台が存在感を示しているヤツは、赤燐をちょこっとつくる装置。三脚架に載っているのは「油浴」、つまり植物油を温めて間接的に加熱する器械だが、本文にも割注で説明されているとおり、鍋そのものだそうだ。
レトルトの位置を高くしてあることについては、くちばしの方に挿したL字に曲げたガラス管の垂直部が「撿壓器ノ長サヲ有セサルヘカラス」、つまり圧力計の長さ以上にしておかねばならない、と説明してあるのだが、「即チ七百六十ミリメートル」と添えてあることからして、要するにこれは水銀柱ミリメートルのことをいっているようだ。なおその先が挿し込んであるのは、水銀を盛ったガラスの筒。反応が進んでレトルト内が減圧しても、逆流した水銀を吸い込んでしまわないようにしている、ということなのだろう。
有栓レトルトの口には「撿溫器」、つまり温度計を挿した栓が嵌めてある。レトルトの中には乾燥した燐(白リンか黄リンだろう)を入れ、炭酸ガスを吹き込んで大気を追い出しておいてから徐々に温め、226℃に至るとその一部が「無形燐ニ化シ洋紅色ヲ呈ス」とある。
ここ☟に書いてある製法と同じことなのだろうとおもう。
https://www.you-iggy.com/chemical-substances/phosphorus/red-phosphorus/#preparation
7枚目は「無水亞硫酸瓦斯」、つまり二酸化硫黄(SO2)を液化する装置。「イ」は洗気瓶、「ロ」は「硫化加𠌃謨」(硫化カリウム K2S)を入れた脱硫管、「ニ」は「鹽化加爾叟謨」(塩化カルシウム CaCl2)を詰めた除湿管、そして「ハ」は「食鹽」(塩化ナトリウム NaCl)の寒剤を入れてその中にY字形に分岐させたU字ガラス管「ヘ」を挿し込んである、「玻璃鐘」と呼ばれる漏斗に似たガラス容器。
レトルトの中には硫酸(H2SO4)が入っていて、これを熱してから挿してあるガラス球から水銀(Hg)を落とすと、☟にあるように硫酸水銀(II)(HgSO4)と水とともに二酸化硫黄の気体、つまり亜硫酸ガスが発生する。
https://www.you-iggy.com/chemical-substances/mercury-ii-sulfate/#preparation
これが装置を通って「玻璃鐘」で冷されると液化し、「チ」の試験管内に溜まる、という仕組み。液体に凝結せず「ホ」の誘導管へ抜けたガスは「石灰乳」、つまり消石灰の懸濁液に送り込んで無害化しているそうだ。
なお、ガスバーナーで焙られるレトルトの載っているスタンドが「レトルト台」で、この名前は今でも使われるが、ここに描かれているのが本来の姿といえそうだ。
さてようやく8枚目、これは「三鹽化燐」つまり三塩化リン(PCl3)をつくる装置。
「イ」のバーナーにかけた「玻璃球」、円底フラスコから塩素が発生する、とあるので、おそらく塩酸が入っているものとおもわれる。洗気瓶として使われている「ロ」は、本書のほかのところで「三頸瓶」と呼ばれているが、これはウォルフびんという、かつては化学実験でよく使われた厚手のガラス容器。二口のと三口のとがある。
https://www.chemistryworld.com/opinion/woulfes-bottle/2500114.article
「ハ」はガス除湿のための塩化カルシウム管、「ニ」は中に砂を少々敷いた上にリンのかたまり二、三片を置いて加熱しているレトルト、「ヘ」は「ホ」の「受器」を冷すための水槽。なお、三塩化リンができたところでさっさと火をとめないと「五鹽化燐」(五塩化リン Cl₅P)になってしまう、と注意書きが添えてある。逆にいえば、この装置で五塩化リンをつくることもできるわけ、だそうだ。
いや〜、「何のためにどうやって使う道具をあらわしている図版なのか」をちゃんと説明しようとすると、けっこう骨が折れるものだww
なおこの図版は、序文「第一版凡例」冒頭に「此書ハアドロフピン子ル氏グローブベゾ子ツ氏著ス所ノ新式化學書」を纂訳した、とあるうちの一冊、すなわちオーストリア生まれの化学者オイゲン・フランツ・フライヘア・フォン・ゴルプ=ベザネツ(Eugen Franz Freiherr von Gorup-Besanez)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7035607/
の化学教科書(Lehrbuch der Chemie)第一巻
https://www.google.co.jp/books/edition/Lehrbuch_der_anorganischen_Chemie/HD14avBvFbcC?hl=ja&gbpv=1&pg=PA151&printsec=frontcover
のものを、細密な木口木版を得意とした彫工、蒼虬堂松崎留吉に写させたもののようだ。