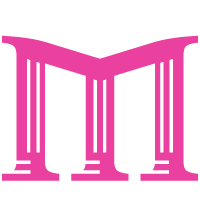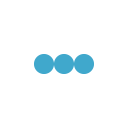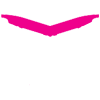化学実験用のガラス器具@明治初期の定量分析解説書
古い化学実験器具の図を見たい、とおもって探してみても、ヨーロッパやアメリカの出版物のものは復刻されたりそういう図をあつめたイラスト集が出ていたりするし、インターネット上でもPDFや素材データその他として公開されているものもあったりするから比較的アクセスしやすいけれども、じゃあ昔の日本で使っていたヤツは、というとこれが割とむずかしい。もちろんインターネット公開されている資料のなかにも出てくるものは実はかなりあるのだが、そもそもどういうタイトルの本がそれなのか識らなければなかなか見つけられないだろうし、少なくとも国内出版物でそういう図版をまとめた本、というのはおよそ目にしたことがない。まぁ商業出版として成り立つだけの需要が見込めないからなのかもしれないが、もしかすると出版側がそう思い込んでいるだけなのでは、という気がしなくもない。
さて、今回は明治ひと桁の時代に出された和本仕立ての翻訳書に載っている、ガラス製の実験器械をいくつか眺めてみることにしよう。巻頭序文によれば、この本は19世紀ドイツの著名な化学者カール・レミギウス・フレゼニウスが著した教科書のひとつ "Anleitung Zur Quantitativen Chemischen Analyse(定量化學分析法)"
https://books.google.co.jp/books?id=i30MAQAAIAAJ
をベースに、アメリカで刊行されたこの本の英語訳版やイギリスの鉱物分析についての本などを参考にまとめた金属鉱物の定量分析入門書で、これの中に実験に使われる化学器械類がいくつか紹介されている。フレゼニウスの化学分析の本を初めて日本に紹介したのは明治5年(1872年)に大阪舎密局の三浦尚之(嘯輔)
https://karin21.flib.u-fukui.ac.jp/repo/AN10517316_Vol.21_51-78__cover._?key=YCDTJS
が邦訳したものがそれらしいが、大阪開成所で学んだ後衛生技師となった飯沼長藏
https://www.jstage.jst.go.jp/article/rcmcjs/12/0/12_0_29/_pdf
の手になるこの本もほぼ同じ時代のもの。19世紀半ばごろに使われはじめたものも含め、1870年代に西洋の道具と実験方法とが、そのころ我が国ではじまったばかりの化学教育現場へも持ち込まれたようだ。なにしろ入ってきたばかりだから、おそらくここに書かれている日本語での呼び名も、訳者がその場で考えてつけたのだろうとおもう。なお掲げた画像のうち、原典で名称と図版とが離れているものについては、その名称部分を切り貼りしてある(まわりに赤っぽい影がついているのでおわかりいただけるかと)。
1枚目の「驗容壜」は全量フラスコ(メスフラスコ)。図版研が架蔵する理化学器械の総合カタログでは最も古い明治末期の田中合名會社『理化學機械藥品目録』五版(明治44年(1911年)刊、以降「目録」と略す)を引きくらべてみると、「計量フラスコ」「容量フラスコ」、別称としてカッコ書きで「細頸劃度壜」などという名前に変わっている。「劃度〈かくど〉」というのは要するに「目盛りつき」ということ。2枚目の「劃度圓壔」はメスシリンダ。目録では「無栓劃度圓筒」として載っている(19世紀には「円筒」を「圓壔〈ゑんたう〉」と書いていたようだ)。3枚目「吸液管」はふりがなでおわかりのとおりピペット。目録では「容量ピペット」 になっている。4枚目「漏液管及ヒ其架」はこれもかながふってあるとおりビュレットとその架台で、目録では「ビウレツト(モール氏)」「ビユレツト保持架臺」とある(ただし、同じカタログ内で「ビウレツト」「ビユレツト」「ビユーレツト」「ビーレツト」などと表記にブレがある……明治らしいといえば明治らしいww)。「モール氏」はこのようにビュレットの下部に流量調節のできる仕組みをくっつけた、フレゼニウスと同国・同時代の化学者カール・フリードリヒ・モールを指す。それから図版の右側の解説にある「樹膠管」は前ページに「ゴム」とルビが振ってある。「短小ナル尖端玻管」は先っぽに取りつけた短いガラス管、「鉸鑷子〈かうせつし〉」はピンチコックのこと(目録では「護謨管挾」)。なおこの架台は木製だが、目録の方では金属製になっていて、台の部分は磁器、腕は黄銅製だったようだ。
5枚目「嘘吹漏液管」は「「ガイ、リュツサク」氏の創製スルモノナルヲ以テ「ガイ、リュツサク」漏液管トモ云フ」と解説されているが、これは現在では使われていない……実験でどう使うのか、本篇のどこかにきっと書いてあるよね、とおもってこの本のアタマからシッポまで斜め読みしてみたのだが、出てこない……この書物、標題に「前編」とついているとおり「後編」卷之上中下+附録も当初は企画されたことが前編卷之上巻頭の目録(=目次)や、ここに掲げた「器械圖解」卷奥附に「後編近刻」とあることからわかるのだが、実は(理由はよくわからないが)結局前編3冊で終わってしまったらしい。おそらく本来は、後編に出てくる予定だったのだろう。で、この変わったビュレットについてちょっと検索してみると、海外サイトに載っている18世紀フランスの化学者ジョセフ・ルイ・ゲイ=リュサック略伝に、彼が1824年に側管のついた改良型ビュレットを考案した、という記事があって、その図のものと構造が似ている。
https://www.bookofdaystales.com/gay-lussac/
そこで原書の英語訳版が公開されていたのでこれが載っているところをみてみると、ここに詳しい説明が書いてあった。
https://books.google.co.jp/books?id=Cf44AAAAMAAJ&pg=PA36
ゲイ=リュサック式は本体と側管との繋ぎ目のところで泡が邪魔しがちなので、モールが改良型を考案した、ということのようだ。因みにその次のページに、この側管を内部に取り込んだ形の「ガイスラー氏ビュレット」というのがあるが、こちらは今でも生き残っているらしい。なお目録をみてみたら、「ビユレツト(ゲールサック氏)」「ビウレツト(ガイスレル氏)」としてどちらも載っていた(ただし後者は図なし)。さておき、原書では脚がついていなくて木製架台で支えるようだが、この「器械圖解」卷では円錐台形のしっかりとした脚部がある。目録にある図版でもやはり同じような脚つきなので、そういう製品が当初から輸入されていたものとおもわれる。
6枚目「迸水壜」は洗浄びんのこと。目録では「洗滌〈せんでき〉壜」になっていた。現在のものは胴がやわらかいプラスティック製で押せば水が出るが、かつてはガラス容器だからもう1本空気抜きの管が生えていたわけだ。7枚目「嘴杯」はビーカー。本篇ではカギカッコつきで「ビーケル」と書いてあって、漢字は使っていない。ところでどうしてこのように大きさ順にたくさん重ねてあるかというと、かつてはこのようなセット売りが主流だったからだ。目録でも5個、7個、8個、12個が載っている。もっと時代が下って昭和あたりからは3個組とかも出てくるが、バラ売りしかしなくなったのはようやく大東亜戦の最中から(多分戦時物資統制の影響だろう)�、というのがカタログをいくつもみているとわかってくる。海外の19世紀半ばごろのカタログをみると、組売りしか載っていない。
https://books.google.co.jp/books?id=vf8qAAAAYAAJ&pg=PA10
https://books.google.co.jp/books?id=1r0LAAAAYAAJ&pg=PA6
どうしてそうだったかというと、そうしないと輸送中に割れてしまうからだったらしい。当時易損品は緩衝材が薦〈こも〉(日本酒の薦樽を覆っているあれ、というのでおわかりいただけるかしらん)とか藁〈わら〉とかで、輸出の場合はそれでくるんで縄でくくったのを木箱に入れて運んでいたから、薄〜いガラスでできたビーカーをそのままひとつひとつ並べて箱詰めして、というのはできない相談だったのだ。20世紀のカタログには1個あたりの単価が出てくるようになるが、あんまり使わない大きさのヤツも毎回買わないとならないのはもちろん不合理だし、それに梱包材や輸送中の振動防止などの技術が向上し、また国内生産もひろくおこなわれるようになっていたこともあって当初の問題は解消していたのだろう。それから、「ビーカー」という語は「ビーク(くちばし)」からきているから「嘴杯」と宛てたのだろうが、かつては鳥のくちばしみたいな注ぎ口がついていないものも少なからずあった、というのもカタログの図版でわかる。8枚目「時儀甲盞」は時計皿。「時儀」は時計の古いいい方、「盞」は小さいさかづきのこと。かつては携帯用時計として一般的だった懐中時計の風防ガラスと成型の仕方が同じだったからウォッチグラスと呼ばれるのだそうだ。なお目録ではすでに時計皿になっていた。
それにしてもどれもこれも、ずいぶんとまた硬い字面を宛てたモンだなぁ、とおもってしまうが、漢文が知識人の当然身につけているべき教養のひとつだった時代ゆえ、なのかもしれない。
追記:ビーカーについて、我が国でも戦前まではばら売りしなかった、と書いていたのは間違いと気づいたので書き直し、セット売りしか載っていない実例として海外のカタログへのリンクをふたつ追加した。
https://muuseo.com/lab-4-retroimage.jp/items/149