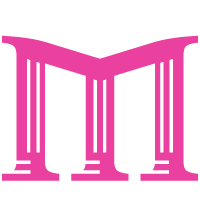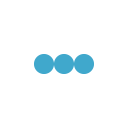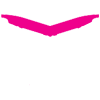- Lab-4-RetroImage.JP Museum
- 17F 農芸畜産学展示室_家畜の部屋
- ペットとしてのウサギ@昭和初期の愛玩動物飼育手引書
ペットとしてのウサギ@昭和初期の愛玩動物飼育手引書
明治の初め、さまざまな西洋の文物とともに舶来種のウサギももたらされ、にわかペットブームが起きたのだが、明治5年(1872年)からそれが本格化し人気の柄のものに高値がついて、投機に入れ込む人が続出し社会が混乱したという。
http://doi.org/10.15083/00031135
あまりのことに明治10年(1877年)対策として高額の課税がなされてブームはしぼんだが、ウサギの毛織物製造の産業課をこころみる動きがそのころからはじまり、明治30年代にかけていくつか会社も立ち上げられたものの、政府がバックアップをしなかったこともあって輸入製品に太刀打ちできず失敗におわったそうだ。大正も末になって、アンゴラウサギを蕃殖してその毛で商売しようという人も現われたが、昭和3年(1928年)あたりから養兎業者が増えてきて、さまざまな種類が飼われるようになったという。
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10076939&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1
その一方で、利殖のためでなく純粋に生活にうるおいをあたえるためのペット飼育が、庭つきマイホームを手に入れた人々の間で流行るようになってきた。今回取り上げるのはそうした時期に出された、一般向けの総合飼育解説書のウサギのところ。
当時はペットショップなどはないから、ウサギを飼うための巣箱は自作する必要があった。1枚目の上のはビールびんの空きケース(2ダース入り木箱)を加工したもので、放し飼いができるような広い庭がない家庭用のもの、2枚目のはもっと広い敷地に拵える、庭木を取り込んで金網で囲った「兎のお家」。図には描かれていないが、金網の外から飼い犬が土を掘って中に入り込んだり、穴掘りの得意なウサギ自身が脱走したりしないよう、「尠〈すくな〉くも地下一尺位〈くらい〉は金網に限りませんが、兎の逃亡の邪魔になる亞鉛板か貫板〈ぬきいた〉を埋込んで置く必要があります。」と本文には注意書きがある。なお1枚目の下はウサギの持ち方を示している。なお今日では「耳はつかまない方がよい」という考え方に変わっているようだ。
3〜7枚目はウサギの種類についての解説に添えてある輸入種の例の図。「ベルヂアン種」はベルギー原産で野ウサギに似ていて、赤茶色の毛で耳や脚が長い。「フレミツシユ種」は「ベルヂアン」とフランス産の大型種「バタコニアン種」とをかけ合わせた中欧産の、当時最大種のウサギで灰色のが多い。「イングリツシユ種」は脊骨に添った1本の縞と、それから胴のわきと眼のまわり、鼻先、耳に黒斑がある特徴的な見た目。「白色メリケン種」は我が国在来種の白ウサギと外来種(どれなのかは書いてない)とを交配させて作った大きな白ウサギ。「ヒマラヤン種」は「露西亞種」とも呼ばれ支那北部産で、鼻・耳・脚・しっぽが黒くそのほかの部分は真っ白、というもの。「ダツチ種」はオランダ産で黒・灰・黄・白とその斑、と柄はいろいろ、写真のようにびしっと塗り分けになっているのが特徴。「ロツプイヤー種」は「耳が素適(<ママ)に大きい英國兎」で毛色は「ダツチ」に似ているが、虚弱なのが欠点。「チンチラ種」は昭和に入ってからひろまった、毛の特に柔らかい種。「シルバー種」はその名のとおり銀色の毛をもつ英国産の割と大きな品種。終いのもこもこしたヤツが「小亞細亞のアンゴラ地方の原産で、佛蘭西〈ふらんす〉で盛んに飼育され」ていたという「アンゴラ種」。白・黒・茶とそれぞれの斑があり、ご覧のとおり非常に毛が長いのが盗聴だが比較的弱いのが玉に瑕、というように解説している。このほかにフランス産のダッチ種の突然変異「ジヤパニーズ種」、イギリスでダッチ種に在来種を交配して作った斑の色が濃い「タン種」、オランダ原産で光の当たり具合により毛色が変わってみえるという「ハバナ種」、ベルギー産で白いのと青いのとがあるという「ベヘリン種」、イギリスでダッチ・アンゴラ・ローブ種などをかけ合わせて作出した緑色の毛の「インペリヤル種」も、図はないが紹介されてある。
さて、8枚目に掲げたのはこの章の最初の部分なのだが、これをお読みになるとおわかりのように、当時家庭でウサギを飼う目的は現在のように単に日常生活のともとしてかわいがるだけでなく、食肉目的もあった。輸出元の西欧諸国ではもちろん食べていたわけだし、我が国でも、鳥肉の一種という方便で昔から食べられていたから数えるときに「1羽2羽」という、とする説があるように、元から馴染みのある人々もある食材だったから、それは自然な流れといえるだろう。しかし、ここに「食肉の矛盾」として書かれているように、飼っているウサギを絞めて食卓にのせる、ということに抵抗を感じる人々が昭和のはじめには既にかなりの数あったことが知れる。