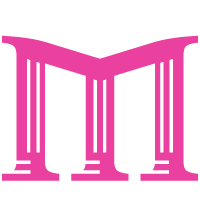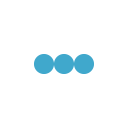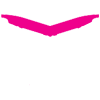- Lab-4-RetroImage.JP Museum
- 25F 器械展示室_工業機械の部屋
- 欧州大戦期の業務用リトグラフ印刷器械@大正初期の化学工業解説書
欧州大戦期の業務用リトグラフ印刷器械@大正初期の化学工業解説書
大正3年(1914年)に勃発した欧州大戦によってヨーロッパからの物資供給が滞るようになり、当時尖端技術を使った化学工業製品の多くを輸入に頼っていた我が国は、戦火からは地理的にはるか遠くにあったにもかかわらず非常に困ったことになった。国内工業は盛んになりつつあったとはいえ、まだまだ技術的にはおくれていて、もちろん熟練工も十分に育ってはおらず、その教育を施そうにもぴったりくる日本語の参考書がなかった。今回はそうした状況で企画された実務家向けの解説書の中から、石版印刷、すなわちリトグラフによる平板印刷に当時用いていた印刷機や色々な道具類の図版を拾ってみよう。
リトグラフは、今日ではアルミニウムなどの金属板を使うことが多く、また石版を使うにしてもその産地はあちらこちらにあるようだが、かつてはドイツ特産の石灰石でしか刷れない印刷法だった(なお当時も、金属版としてアルミニウム版と亜鉛版はおこなわれており、この本にも石版に引き続いてそれぞれ解説されている)。当時すでに石版印刷による美麗な印刷物が国内でも作られて人気を博するようになっていたが、それに用いる印刷機にしても、それから製版に使う描画用品なども輸入品が多かったため、戦争で物流が停まってしまって鉄鋼材料の価格がいきなり上がり、それにつられて器械類の値段もはね上がったらしい。例えば1枚目の手刷印刷機は当時「第三號機」と呼ばれる、四六判四つ切りを刷る最も普通に印刷工場で使われていたものだそうだが、この本によれば戦前は25〜26圓だったものがこの当時には45〜46圓に、となんと1.8倍にも高騰していたことが解説されている。大正4年(1915年)の大卒初任給が35圓ほどだったという
http://sirakawa.b.la9.jp/Coin/J077.htm
から、その程度がしれよう。なお手動印刷機の「第二號機」は菊判半截、「第一號機」は菊全判が刷れるものだったが、これらはたいてい製版のために使われ、印刷は専ら「第三號機」でおこなわれていたという。
2枚目の大型機は「動力使用印刷機」で、当時のドイツ製最新鋭機。四六判四截、四六判二截、四六全判、菊判半截などのヴァリエーションがあり、電動機のほか石油エンジンや石油ガスエンジンを動力源としていた。印刷能力は職工が手刷りで1日10時間に600枚刷るところを、これらの動力機を使えばその10倍は確実に刷れたそうだ。ただし初期投資額はもちろん比較にならないほどで、導入できる工場は限られていたようだ。
3枚目の卓上機は印刷工場では使われない小型機で、石版印刷を発明したプラハ生まれのドイツ人劇作家兼俳優のヨーハン・アロイス・ゼーネフェルダーのが自ら使う台本を刷った
http://www.joshibi.net/hanga/history/1700.html
ように、自費出版や商店の広告宣伝などに使われたのだろうし、もちろん美術家の版画作品も生まれたことだろう。その下の
「ルーラ」は「印肉」、つまりインクを版面につけ伸ばすのに使う、今でいう「革ローラー」で、木製の円柱のまわりに舶来の「紋羽(起毛加工を施した綿布の一種。フランネルに似ているそうだ)」かフランネルを重ならないように巻きつけ、その上に上等の牛革をかぶせて縁と縁とを毛抜き合わせで縫い付けて覆ってある。「墨ルーラ」と「色ルーラ」の2種類があって、前者は革の裏側の粗い面、後者は反対に毛の生えていた表側の滑らかな面を外側にしてある。これは買ってきてすぐに印刷に使えるものではなく、ワニスを塗ってはインクの上で日に1、2度ころころやるのを5、6日も繰り返したあとに余分のワニスを拭き取って日に2、3回インクを塗ってはころころやるのを2、3日やってからインクをへらでこそげ落としてからまた同じことをやるとおよそ2週間後には表面がつるつるになる、という「ルーラ平〈なら〉し」をやらないといけなかったそうだ。ただしこれは「墨ルーラ」のならし方で、「色ルーラ」の場合はワニスの後のインクを拭き取らずに揮発油で洗い落としてから布で十分に拭きこすってから10日ばかりおいておくと、元々滑らかな表面がさらにつやつやになってようやく使えるようになるのだそうだ。なお「色ルーラ」は表面のインクが乾いて固まってしまうと次に刷るときに綺麗に仕上がらなくなるので、使いおわるたびに揮発油か石油で洗って布で拭き取る作業が欠かせなかったらしい(「墨ルーラ」は前日のインクをこそげ取りさえればすぐ使えるそうだ)。いずれにしても手間暇がかかる話だ。当時はまだゴムローラーはなかったらしい。ここでご参考までに、武蔵野美術大学「造形ファイル」サイトに公開されている現代のリトグラフ用具をご覧いただいておこう。
http://zokeifile.musabi.ac.jp/%e3%83%aa%e3%83%88%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e7%94%a8%e5%85%b7/
↑の下の方の「関連項目」のところに、個別解説のある道具もある。
4〜6枚目は石版の製版に用いる道具いろいろ。6枚目左側にある「第十七圖」はキャプションに「クライオン挼」とあるのだが、本文には「クライオン挾〈はさみ〉」とあって、「挼〈おさえ〉」というのは出てこない。こんな滅多に使わないような活字をわざわざ間違って拾うだろうか? という疑問は涌くのだが、8枚目の図版キャプションも「研磨機」が「研麿機」とあからさまに誤植をやらかしているので、多分ここも間違いなのだろうと想像している。この「クライオン」というのはリトグラフで砂目立てした石版面に絵を描くときに使う、脂肪分の多い特殊なクレヨン。今では「リトクレヨン」と呼んだりするらしい。
http://zokeifile.musabi.ac.jp/%E3%83%AA%E3%83%88%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%A8%E3%83%B3/
今日の市販品はメーカーによって硬さの呼び方がばらばららしいが、当時は硬質な方から順に「號外」「一號」「二號」「三號」
の4種類だったそうだ。なおこの本には「クライオン」の作り方も載っていて、シェラックの多い「シエラツク、クライオン」、羊脂を使いシェラックを含まない「エンゲルマ氏クライオン」、シェラックが少なく鯨油から作った蝋と白蝋(晒し蜜蝋)を使う「デレー氏クライオン」の3法が紹介されている。石版用の石材は先にも書いたように、現在も最上とされるドイツ・ゾーレンホーフェン産のものに当時は限られるとされていて、濃鼠色、淡鼠色、黄色の3種があった。鼠色の方は緻密で細密画に適し、黄色のものはそれよりも硬度が低く表面がやや粗いため直描きや細密でない転写などに用いたそうだ。大きさは用途別に作られていて、「美濃版石」とも呼んだ原版用の「原版石」、印刷用として最もよく使われる四六判四截大の「柾版石」、その名のとおり菊判半截を印刷する「菊半石」、菊全判を印刷する「菊全判石(この本には「菊金判石」とあるがこれも誤植だろう)」、同じく「四六半截石」「四六全判大石」の6種類が主に市販されていたという。
7枚目の「鑄鐵製研磨具」は円い穴の中に金剛砂
http://zokeifile.musabi.ac.jp/%E9%87%91%E5%89%9B%E7%A0%82/
を入れて石版石面を研磨するのに使う。この道具が砂目立てには最適、と書いてある。8枚目の「研磨機」は大規模工場で使う業務用で、当時この図版にある器械が最も一般的だったそうだ。