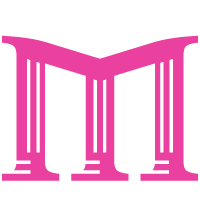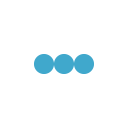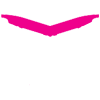- Lab-4-RetroImage.JP Museum
- 25F 器械展示室_工業機械の部屋
- セルロイドを造る機械たち@昭和初期の一般向け工業製品工程図解書
セルロイドを造る機械たち@昭和初期の一般向け工業製品工程図解書
今やほとんど石油製品に取って代わられて、国内では全く造られなくなってしまったセルロイドは、その独特の風合いや手触りで根強い人気を保っている合成樹脂だが、戦前には世界市場で圧倒的なシェアをもつ有力な輸出品だった。元はアメリカで考案された技術だが、可塑剤として使われる樟脳を採るクスノキが東アジアにしか生えておらず、明治28年(1895年)にその精油を豊富に供給できる台湾を併合した日本は、それまで輸入していたセルロイドの国産化に邁進するようになったのは自然な流れだったろう。なにしろ、繊維素(セルロース)の原料となる木綿ぼろも加工に添加するエタノールも国内で安定して確保できるものばかりだったからだ。
今回紹介するセルロース製造工場内部の図版は、この本の序文に列挙されている材料提供に協力した団体等一覧、及びこの章の解説内容からして大日本セルロイドのものとおもわれるが、同社は大正8年(1919年)に8社が合併してできた企業なので、そのうちのどの場所なのかはわからない。日本化学会が認定した化学遺産第009号「日本のセルロイド工業の発祥を示す建物及び資料」には、そのうちの1社堺セルロイドの工場内部写真が載った『記念帖』が含まれるが、その紹介記事
http://www.chemistry.or.jp/know/doc/isan009_article.pdf
で見くらべてみると、そちらよりはだいぶ狭いような印象をうける……が、それは単に写真の撮り方の違いによるのかもしれない。この本の解説によれば原料となる硝化綿(ニトロセルロース)の製法にはいろいろあるのだそうだが、当時最もひろく行われていたという「壺式硝化法」がここでは図解されている。1枚目の、タイトルとともに写っている製品は靴べら、交通機関の回数乗車券を入れる透明ケース、その奥の手提げ籠のようなものはおむすび入れかしらん。
さて、2枚目の工程図解に沿って写真を眺めてみることにしよう。まず最初の「ぼろの撰別」は、染めたぼろが混じると後にセルロースに着色する際に色味が意図と違ってしまうため、白いものだけを選り分けておく必要あっての作業だそうだが、よく視ると集塵機の下で立ち働く女性とおもわれる作業員はみなマスクをしていて、おそらくは埃がもうもうと立ちこめる、いかにも身体によくなさそうな作業環境におもわれる。こうした単調な選別作業は、昔はだいたい女性ばかりが充てられていたことが、古い図版を数多く眺めていると読み取れる。
2番目の「捏和〈ねっか〉機」は硝化綿に樟脳とエタノールを加えて密閉槽で熟成させた餅のように粘り気のあるセルロイドの塊を温めながらこねる機械で、色を着ける場合はここで着色剤を加える。3番目の「壓延機」は、捏和により均一に混ざって僅かに黄色みを帯びた透明になったものをこれのローラーにより蒸気をあてながら圧し延ばして板状にする。セルロイドは元々、ビリヤードの球を造るのに用いられる象牙の代用品として考え出されたものだが、同じく動物原料の鼈甲の模造品や、その他の美しい模様は、色彩や透明度の異なるセルロイド塊をこね合わせ具合を巧く調整したり、あるいは複数種の板を重ね合わせて圧縮したり、というような職人の工夫と技術とにより作り出されるのだそうだ。そうしてできあがった板には気泡が含まれているので、それを温めながら水圧をかけて追い出し、畳くらいの大きさの分厚い板状になったものを4番目の「裁斷機」で切り揃える。表面に艶出しをする場合には板が冷えてしまわないうちに5番目の「光澤機」にかける。さらにバフで磨いてつやつやにすることもあるという。最後の「成形作業」は人形などの中空の製品を造る工程で、真鍮製の鋳型の間にセルロイド板を二つに折りたたんではさんで加熱し、折り曲げた生地の間に細い管で蒸気を吹き込んで型に密着させてから空気を吹き付けて冷すやと形ができあがる。あとは鋳型から外してはみ出た余分な部分を削り、色を塗ったり艶出ししたり細かい彫り込み加工などを施して完成させる、という手順が解説されている。
セルロイドは加工がしやすく、一度固まると変形しにくく、じつにさまざまな用途に利用されていたが、非常に燃えやすいという欠点がある。卓球の球は今でもセルロイド製のものが使われているが、材質が劣化してくるとその分解熱で自然発火してしまう危険性がある、と日本卓球協会が警告している。
http://www.jtta.or.jp/Portals/0/images/news/2016/kikenseruroido.pdf
今のコレド日本橋のある角地にかつてあった白木屋百貨店で昭和7年(1932年)暮れに起きた昭和初の高層建築物火災は有名だが、売り場の電飾を修理しようとして誤って電線をスパークさせた火花がクリスマスの飾り付けに引火し、それがさらにそばのセルロイド製人形などに燃え移ってあっという間に火の海になったという。
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/libr/qa/qa_38.htm
https://bunshun.jp/articles/-/19515
大正〜昭和初期の映画雑誌を読んでみると、各地の映画館でしばしば大勢の死傷者を出す痛ましい火事を伝える記事が出てくるのだが、これも当時の映画フィルムがセルロイド製だったからで、映写機の光源に使っていた炭素アーク灯の熱とか、冬場にそばにある暖房用火鉢にうっかり近づけたりとかで一旦燃え上がるともう手がつけられなかったらしい。この章の終いには「特殊セルロイド」として大日本セルロイドの製品がいろいろ載っているが、その中には不燃性のものもある。しかしこれが大いに普及しなかったらしいのは、どうやらコストが需要に見合わなかったかららしい。同社から昭和8年(1933年)に写真フィルム事業専業として分かれた富士寫眞フイルムは国産映画フィルム製造のさきがけだが、早々に開発に着手していた不燃性フィルムベースの量産化に目処が立ったのは昭和27年(1952年)も暮れになってからのことだったそうだ。
https://www.fujifilm.co.jp/corporate/aboutus/history/ayumi/dai2-04.html
大東亜戦中は外交関係の杜絶、綿火薬としての用途も大きかった硝化綿の軍需対応による工場の業態転換などで停まっていた輸出も、工場設備の戦災被害が小さかったこともあり戦後には盛り返し、昭和24年(1949年)には再び世界のトップシェアを握った。難燃化に向けた取り組みも続けられていたそうだが、敗戦に伴うインフレーションの影響が大きかった上、昭和20年代半ばからは発火の危険性もなく安価な石油系が出まわるようになり、燃えやすさが改めて大いに問題視されれたことに加え、価格面でもコスト割れして市場がみるみるしぼんでいった。それからわずか10年ほどで、セルロイドは樹脂製製品に占める割合は1%を切ったらしい。そして平成8年(1996年)には、ついに国内生産は打ち切られてしまった。現在国内需要にこたえている製品はすべて輸入品だ。
http://www.celluloidhouse.com/kenkyu24.pdf
セルロイドは埋めておけばちゃんと土に還る。いつまでも環境に残る石油系プラスティックによる生物への悪影響が大いに問題になっていること、代替品としてのいわゆるバイオプラスティックが必ずしも無害なかたちで生分解されない上、透明なものを造るのも難しいことを考えると、セルロイドの改良を今一度研究してみる余地はないのかな、とおもってしまう。