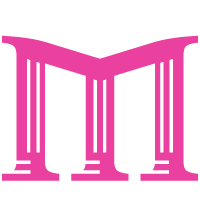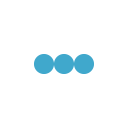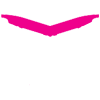- Lab-4-RetroImage.JP Museum
- 1F 博物(動物学)展示室_哺乳類の部屋
- ねこの観察・うさぎの観察@明治末期の子ども向け理科観察手引書
ねこの観察・うさぎの観察@明治末期の子ども向け理科観察手引書
20世紀が明けて、学校教育を受けた世代が成人して子どもを持つようになると、理科趣味を誘う大人向けの通俗科学書とともに、学校や家庭での理科教育の手助けを企図した子ども向けの理科の本も出版されるようになった。今回取り上げるのは、そうした出版物の中では早い時期のものとおもわれる小冊子から、身近な哺乳類としての「ねこ」と「うさぎ」の観察のところ。
ちなみに著者の野田瀧三郎は東京高等師範學校文學科の出身だそう
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/12271/1/kyouyoronshu_437_%281%29.pdf
で、この本の序文にも「自分はこれまでの學修は文科ぢや。」と書いている。「中の記載は箇條がきで、ほんの骨だけ、それに肉をつけるのが、教師たち、親たち、兄たち、先達たちのつとめぢや。」とあるところから、おそらく尋常小學くらいの子が教師や親きょうだいなどとともにみることが想定されていることがわかる。大きな文字組みが子ども向け、各章の終いの小さな文字組みは指導にあたる年長者向けということになろう。
1枚目と5枚目の図版は、どちらも基本的には当時のたいていの動物教科書に載っているものと同じだが、それらよりもやや図案化されている、というか略画っぽく描かれている。精確性よりも、まずは小さな子どもに対象への興味を持ってもらうことを優先したからかもしれない。文章も教科書よりはかなりくだけていて、誘いかけるような語調だし、終いの方にはテーマの動物の名が入った慣用句や童謡、俳句など、より文学に寄ったおまけもついている。序文で著者が「我が國民は妙に文學的のことを好み、理科的のことをきらふ。のみならず、文學を上品とし、理科を下品なこととしてゐる。好惡はしかたがないとしても、上品、下品のしなさだめはちと酷ではあるまいか。」と歎じているが、下品とまではいわなくとも文学にくらべて科学は取っ付きがわるい、と毛嫌いする向きが少なくなかったようで(もしかするとその辺、今の世もあんまり変わらないんじゃないの、とゆー気もするけれど……)、明治大正期の一般向け科学書には、文系の著者ばかりでなく理学士の手になるものでも、こうした要素がところどころに挟み込んであることが少なくない。
最初にまずどこにでもいそうなネコを持ってきて、その後に出てくるウサギについてはネコとの比較をうながしているところがおもしろい。問題集と違って、「比べてごらん」と問うてもその模範解答が安直に書いてあったりはせず、あくまで自らよくみて体感した上で考えさせようという姿勢に好感がもてる。ふりがなが単なるよみではなく、その意味をかみくだいた傍訓になっているのは、いかにも明治期らしい。
2枚目のネコの毛について、「二色〈ふたいろ〉ある」というのは、その後の解説でおわかりのように毛色の話ではなくて、上毛(刺毛)と下毛(綿毛)との二種類がある、という意味。イヌよりもネコの方があったかい、というのは実際に彼らに触れてみなければわからないことだ。3枚目初っぱなの「四、蹠」はあしのうら。「やわらかい肉嚢〈にくぶくろ〉」というのはお察しがつかれるかとおもうが肉球のことをいっている。「肉球」という語はいつから使われはじめたのか、ちゃんと調べていないのでわからないが、そんなに古いことではなく、早くとも戦後からではないかと想像している。それよりも前はどうも統一用語がなかったらしく、文献によりさまざまな呼び方が出てくるが、「肉嚢」という例は今のところこの本だけ。「七、齒」のところに「猫は猛獸であることがわかります」とあるのが興味を惹かれるが、4枚目右側の大人向け解説のところにより詳しくその論拠が書いてある。「習慣」や「摘要」のところの表現が「ニャーオ。ニャニャ。」「舌——ざらざら。」とオノマトペを使ってみたり「おめかしをする。」などと、教科書ではちょっと出てこないようなやわらかさでたのしい。「四、じゃれ、ほとたへる。」の「ほとたへる」という語ははじめてみるので、「これってもしかしたら、ごろごろうにゃうにゃする、って意味かな〜」などとおもいつつ『言海』『ことはのいつみ』『辭林』『和漢雅俗いろは辭典』『俗語辭海』など手近に積んである明治末期〜大正前期くらいの辞書をいくつかひっぱってみたのだが、意外や意外どれにも出てこない……ありゃ。しばらく悩んだ揚げ句、ひょっとして「じゃれる」の上方語「ほたえる」
https://www.weblio.jp/content/%E3%81%BB%E3%81%9F%E3%81%88%E3%82%8B
のおつもりなのかも、とおもい至った。文語だと「ほたゆ」なので下二段活用で「ほたへる」にはならないのだが、元々日本語ってヤツは正書法がなく、かなづかいがどうこう小うるさくなったのは右傾化がすすんで国粋主義が幅を利かすようになってからで、少なくとも明治期まではその辺かな〜りゆるかった(例えば「さうではない」の口語「さうぢやねえ」が江戸期の草紙などでよく「ねへ」と書いてある)ようだから、あり得ることではある。
おまけのところ、はじめの3つは慣用句だろうが、「猫のこし。」というのはちょっとわからない。「猫の腰」ならば腰抜けを揶揄する「河豚喰った〜」なのかもしれないし、「猫残し」ならば小さい子どもが食事のときにきれいに食べないことをいう「猫の食残し」がおもい当たるが、さてどうなんだろう(子ども向けの本だから後者にちがいない、とおもっておきたい)。次の「くるくるまはつてニャニャの目。」というのは、水谷まさるの歌詞に中山晉平が曲をつけた「上がり目下がり目」
http://www.worldfolksong.com/songbook/japan/doyo/agarime-sagarime.htm
をすぐ連想させるが、実はこの歌詞が収録された昭和4年(1929年)刊の水谷の『歌時計 童謠集』
https://www.aozora.gr.jp/cards/001074/files/42285_23907.html
には「――むかしの遊戲唄につけ足して/今の子供たちにおくる――」と添えてあるそうで、あるいはこれがその原型なのかもしれない。その次の俳句は18世紀に活躍した俳人橫井也有時般〈ときつら〉
http://urawa0328.babymilk.jp/haijin/yayuu.html
の俳文集『鶉衣』に収められている「猫自畫賛〈ねこのじがさん〉」
http://shinshu-haiku-pr.namaste.jp/yayu/y_uz14.html
にある句のようだ。なお「二十日草」というのは、大正期に新古畫粹社から出された齋藤隆三『畫題辭典』に「牡丹の異名なり。」とある。元は白樂天の詩からきている由。
http://www.arc.ritsumei.ac.jp/opengadaiwiki/index.php/%E4%BA%8C%E5%8D%81%E6%97%A5%E8%8D%89
さて次はウサギの方を眺めてみよう。6枚目の「三、脚」の「注意事項」のところ、「兩足不揃のために甘〈うま〉く、え、あるかぬ。」というのは左右の脚が、という話ではなくて、その上に書かれている「前足は短く、後足は長くて……」バランスがよくないから(例えばネコのようには)うまく歩けない、ということだろう。「え、あるかぬ。」は古語の否定形「得歩かぬ」(どーしてわざわざそういう表現にしたのかはわからないが……文学の「上品」ぶりのあらわれだろうか?)。次に「四、足」があって、これは前項の「脚」が肩・腰より先全体を指しているのに対してくるぶしよりも下の部分を別途取り上げているわけだが、先に言及した「前足」「後足」は前脚・後脚を指しているのは明らかで、やはり類義漢字の使い分けは結構気ままといえる。「注意事項」に書いてあるように土の上で暮らすウサギの爪はネコの爪と違って磨り減っているが、それは「猫のやうに保護されてゐないから」
だけではなく、そもそもの生え方が違うからでもある。ネコは頻繁に爪磨ぎを自らおこなって、その際磨り減った爪はカートリッジのように剥けおちてその下から鋭いのがあらわれるが、ウサギの場合は磨り減ってくれないとどんどんそのまま伸びていってしまう。だから室内飼いのペットなどは、ネコと違って飼い主がしょっちゅう爪切りしてやらねばならないらしい。
7枚目、「六、目」のところの「耳の附きどころがこんなですから、……」というのは「目の附きどころが」の誤植ではないかとおもわれる。「習慣」の「一」にある「夕暮に野原へ出て何かくひよるのを……」は、「何か食べているのを」という意味だろう。「効用」の「一」の「衣類の料」はもちろん原材料の意。8枚目の大人向け解説にも「皮は多少價〈あたい〉を有する。」と補足してある。この「効用」、つまり人間にとってどう役立つか、というのは19世紀の博物教科書などには必ずといっていいほど書いてあって、ネコの場合は鼠をとる、皮を三味線の胴に張る、などと当然のように解説されていたものがこの本ではみられないのは、もしかしたら時代のうつり替わりにしたがって、ネコに対する人々(特に子ども目線を意識する人たち)の意識が少し変わってきている(が、一方ウサギはまだペット飼育の対象としてとらえる人があんまりいない)ことを示しているのかもしれない。