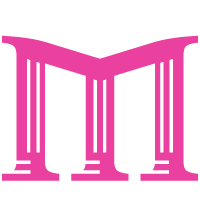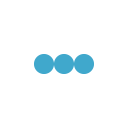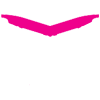- winw00d Museum
- 1F Traffic
- 『TRAFFIC』
『TRAFFIC』
このアルバムは、制作に先立って、スティーヴ・ウィンウッド、ジム・キャパルディ、クリス・ウッドの3人はデイヴ・メイソンを説得し、再び4人でのレコーディングを実現させ、再び彼が脱退するまでのわずか9カ月のあいだに完成している。デイヴがトラフィックと再会したのは、ちょうど渡米していた1968年4~5月頃と思われ、互いにそれぞれ5曲前後の持ち歌があった。トラフィックに復帰したデイヴは、主にニューヨークのレコード・プラント・スタジオで録音することになった。デイヴとその他のメンバーとの音楽的な相違が如実に現れている点も、このアルバムの特徴といえる。スティーヴ、ジム、クリスの3人のペンによる曲と、まったく趣向の異なるデイヴの曲が交互に並ぶ本作を聴くと、それを明確に感じることができる。スティーヴが関わった曲は、R&Bをベースにした曲調にソウルフルなヴォーカルが絡むどちらかというと渋めの方向性、一方デイヴのほうはスワンプやフォーク寄りの曲調に、持ち前のキャッチーなメロディが際立っている。そんな両者が生み出したタイプの異なる作品が、絶妙なバランスをもって1枚のアルバムに共存し得たことが、成功の要因であったといえる。(全米17位、全英9位)
ポップセンスに溢れるデイヴの曲「You Can All Join In」で幕を開ける。アコースティックギターをデイヴが弾き、リードギターとベースはスティーヴが担当、ジムのドラムズにクリスのテナーサックスも活躍する。雰囲気はガラリと変わってウィンウッド=キャパルディ作の「Pearly Queen」が続く。幻想的で黒っぽい雰囲気のメロディにシュールな歌詞も素晴らしく、トラフィック・ソングのなかでも突出した完成度を誇る名曲。4月にレコード・プラントにて録音されており、スティーヴはオルガン、ギター、ベースとマルチに演奏。エンディングのハーモニカはデイヴ。「Don’t Be Sad」はデイヴの作品で、泣き節のヴォーカルが曲調にふさわしい。デイヴはギターとハーモニカをプレイ、スティーヴはオルガンとソロで歌うパートもあり、デイヴのヴォーカルとのコントラストが面白い。スティーヴの黒っぽいハイトーンヴォーカルが冴える「Who Knows What Tomorrow May Bring」は、ジムのドラムズとパーカッションにスティーヴのオルガンがリード。クリスとデイヴは録音に携わっておらず、シンプルな曲構成に抜群のセンスを感じさせる。シングルヒットしたA面ラストの「Feelin’ Alright?」は、トラフィックのキャッチーな面を代表するデイヴ作フォーク・ポップの名曲。リードヴォーカルとアコースティックギターはデイヴ、ピアノとコーラスをスティーヴがバックアップする。
「Vagabond Virgin」はデイヴとジムの共作曲でリードヴォーカルもこの二人が歌う。リードとアコースティックギターはデイヴ、ピアノはスティーヴ、クリスはフルートを吹いている。「Forty Thousand Headmen」はデイヴが脱退していた1月にロンドンのオリンピック・スタジオで録音した曲で、ファーストアルバムの雰囲気と後期トラフィックのスタイルを合わせ持つような作品。クリスのフルートが幻想的な雰囲気を創りだし、スティーヴの物憂げなヴォーカルと解け合う。スレイベルとコーク缶の効果音もクリスによる。「Cryin’ To Be Heard」はドラマティックに盛り上がるデイヴの力作で、多彩な表情を見せるヴォーカルが素晴らしい。またスティーヴによる絶妙なバックヴォーカル、ハープシコード、オルガン、クリスのサックスなどが効果的な彩りを加えていく。儚いメロディのクラシカルな「No Time To Live」は、静寂に包まれた夜に奏でられる悲歌のような曲で、むせび泣くサックスと哀愁を帯びたスティーヴのヴォーカルとピアノが美しい。デイヴはオルガンで参加、オリンピック・スタジオで5月に録音された。最後の「Means To An End」はノリの良いカントリー風のナンバーで、ジムのドラムズとパーカッション以外の楽器とヴォーカルはスティーヴによる。ブラインド・フェイスのステージ・レパートリーにも加えられた。プロデューサーは前作『Mr. Fantasy』と同じジミー・ミラー。エンジニアはエディ・クレイマーに加え、グリン・ジョンズ、ブライアン・ハンフリーズ、テリー・ブラウンの名がクレジットされている。アルバムのデザインコンセプトはジム・キャパルディが担当している。