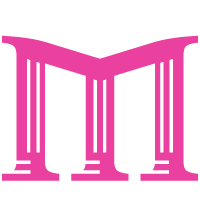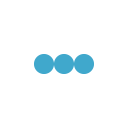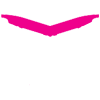書名の翻訳をめぐる冒険
裸の王様 / アンデルセン https://muuseo.com/molo-molo/items/65 𝕄𝕠𝕝𝕠 𝕄𝕠𝕝𝕠 𝔻𝕖𝕤𝕚𝕘𝕟 大学のとき教科書で使っていた、アンデルセンのドイツ語訳が出てきた。原題はDes Kaisers neue Kleider。直訳すると、「皇帝の新しい洋服」となっている。「裸の王様」という日本語訳が誰によるものかはわからないが、なかなか素晴らしい訳じゃないだろうか。オリジナルの「新しい洋服」という語には、おそらく「あれが王様の新しい洋服だってさ!」といった皮肉なニュアンスがあるのだろう。しかし、それをそのまま日本語にしたのでは、いまいち伝わりにくい。そこで「裸の王様」という名訳が生まれたのだろう。実際、「知らないのは本人だけ」という意味の慣用句として定着しているところを見ると、この翻訳は大成功といえる。 もうひとつ名訳で思い浮かぶのは、サン=テグジュペリの『星の王子さま』である。フランス語の原題はLe Petit Prince。「小さな王子様」である。実際、近年刊行されたいくつかの新訳では、この「小さな」というストレートな翻訳が採用されている。だが、内藤濯による広く知られた「星の王子さま」という訳には、どのような思いが込められているだろうか。この物語の冒頭に出てくる、有名なエピソードがある。それは、ゾウを丸呑みにしてお腹の中でこなしているウワバミの絵である。この絵をちっとも理解しない大人たちに、主人公は丁寧に説明するのだが、「そんなことより歴史と文法と算数に精を出しなさい」と言われてしまう。そして、かわりにゴルフや政治やネクタイの話をすると、「こいつは物わかりがいい人間だ」と喜ぶのだ。大人たちは図体ばかりでかいくせに、なんにもわかっちゃいない。原題の「小さな」には、そうした大人たちへの批判が込められているような気がする。だが、それをそのまま日本語にしても、大きさを表す意味にしか思われないのだ。「星の王子さま」という訳は、もちろん星々を旅する主人公の姿になぞらえたものだろうが、同時に子供の透き通った純粋さをもあらわしてもいるのではないか。 書名の場合、「訳さない」という訳も存在する。印象深いのはやはり、村上春樹による『キャッチャー・イン・ザ・ライ』だろう。これは英語だから許される訳し方とも言える。ドイツ語やフランス語だったら、このような芸当は、採用したくてもできないだろう。しかし、いくら英語が身近になったからといって、翻訳を回避してもいいものだろうか。そんな疑問も感じないではない。この小説は原題そのものが破格というか、おかしなところがあって、それも含めたオリジナルのニュアンスを再現するために、あえて翻訳しないという選択をとったことは十分に想像できる。だが、翻訳者である以前に作家でもある村上の中に、忸怩たる思いは1ミリもなかったのだろうか。